意外にハマる地味なクチン
- dish japan

- 2019年4月8日
- 読了時間: 5分
マレーシアのクチン、 日本人には馴染みが少ない街ですが、「ゆる〜くて、やさしい」独特の雰囲気を持っています。
ボルネオ島にあるサラワク州の州都で、人口65万人の大きな町です。
先住民族が多く暮らす地域なので、半島部マレーシアとは異なる生活文化に触れることができます。 街の中心にはサラワク川が流れ、遊歩道が整備され市民や観光客の憩いの場になっています。


クチンは自然に囲まれ、「森林の町」の別名があります。
クチンとはマレー語で猫を表し、この街は猫の街として有名です。町のあちこちに猫の像があり、世界初めての猫博物館があります。そこで、「猫の町」とも言われます。
南北に分かれるクチンのうち、北クチン特別市の紋章にも猫があしらわれていました。

壁画


観光編
1.ネコ博物館
ネコ博物館はクチン北市役所1階にあります。 猫お写真、置物、切手さらに剥製やミイラまであります。 猫グッズも販売されています。ねこ好きには楽しい博物館です。

入場チケットは要りませんが、館内で撮影するには有料です。設備の大きさにより値段が違いますが、高くないです。


世界各国のありとあらゆる猫に関するコレクションが展示されています。
懐かしいなめ猫、招き猫、ドラえもん、キティちゃんなど日本のものも結構幅を利かせています。






2. ウォーターフロント
サラワク川沿いに約900mにわたって続く遊歩道で、オープンカフェや売店が並び、夕暮れ時には地元の人々の憩いの場になっています。
対岸にはホワイト・ラジャ時代の歴史的な建物を眺めることができ、両岸は橋ではなく渡し舟が水上タクシーとして活躍しています。
周囲には見どころも多いので、時間をかけて回りたいエリアです。

クチンはサラワク川によって北市と南市を分けられています。南市は中国人が多く、北市はマレーシア人が多く住んでいます。

サラワク川の上はS型の橋があり、現地のおすすめスポットです。



お手頃価格で楽しめる遊覧船もありますので、ぜひ乗船してみてください。
クチンの爽やかな空気を味わえば、きっと旅の疲れも癒されるでしょう。


3. サラワク文化村
クチンのあるサラワク州には、26以上の民族が住んでいると言われています。
サラワク文化村では、 サラワクを代表する7つの先住民族の伝統的家屋を復元し、それぞれの民族の住人が出迎えてくれます。
1日2回ホールでカルチャーショーが行われるほか、レストランではサラワク独自の料理も味わえます。
「生きた博物館」とも呼ばれているこの村では、貴重な先住民族の人の話やプレゼンを聞くことができ、彼らについて楽しく学ぶことができます。




4.バコ国立公園
南シナ海に面したサワラク州最古の国立公園です。州都クチンからアクセスしやすいロケーションですが、海、ジャングル、河川と、変化に富んだ自然を一挙に満喫できるところが最大の魅力です。



ボルネオ島に生息するほぼすべての植物を見ることができる多様性に富んだ自然生息地であり、霊長類、ネズミジカ、テングザル、ヒゲイノシシ、ジャコウネコ、カワウソ、イソギンチャク、ヒトデなどが暮らしています。
自然に触れながらさまざまな動植物に出会える全16のトレッキング・コースがあり、トレイル沿いでも動植物を間近に観察することができます。
海岸線には長年の浸食でできたアーチ状の岩のオブジェが点在し、マングローブの森ではテングザルやシルバーリーフモンキーが生息しています。

5.セメンゴワイルドライフセンター
オランウータンを野生に戻すための保護区です。
8時半~と14時半~の毎日2回餌付けの時間になると森の奥からゆっくりとオランウータンがやってくる様子を観察できます。
ただし、ここは観光客のための動物園ではありません、広大な保護区の森の中で自由に暮らす彼らが自力で餌を見つけている時には餌付け場所にやって来ないこともあります。









6.サラワク博物館
ホワイト・ラジャ時代の1891年に建てられたもので、東南アジアで最も素晴らしい博物館の一つとされています。
1Fにはサラワクに生息する動物の標本が展示され、2Fには先住民族の家屋、日用品、生活習慣や文化にまつわる模型や写真などが多数展示されています。

グルメ編
1.サラワク・ラクサ(Laksa)
マレーシアを代表する麺料理のサラワク版です。ココナツミルクをたっぷり使ったスパイシーなスープに、細い麺、海老を乗せて食べるのが特徴です。

2.コロ・ミー(Kolok Mee)
サラワク州では定番の、スープなしの麺料理です。麺の上にチャーシューやかまぼこをトッピングして、特製ダレをかけて食べます。

3.ウツボカズラ飯
マレーシアの山岳民族の間で作られている料理です。
現地の人から聞いたところによると手のひらサイズのウツボカズラをつかい、中にお米と赤マメ、場合によっては鶏肉を入れて、袋ごと蒸すそうです。 バナナの葉をつかった料理や笹の葉をつかったちまき、押し寿司のような感覚で 滅菌になり、持ちはこびしやすく、山歩きの際の携帯食糧にもってこいだそうです。

4.サテ(Sate)
発祥はインドネシアのジャワ島で、アラビアからの移民の料理を改良した料理と言われます。
マレーシアでも鶏肉を中心としたサテは代表的な料理のひとつとされています。
このため、官製の航空書簡に絵と作り方がかかれていたり、外交パーティーでも用意されるほどです。マレーシアではクトゥパ(ketupat)と呼ばれる椰子の葉に包んだ米飯と、キュウリ、玉ねぎなどの付け合わせがいっしょに出されることが多いです。

5. ラピスケーキ
ラピスとはマレー語で「層」という意味。ラピスケーキはカラフルなスポンジが層になったケーキで、サラワク州の「ご当地スイーツ」です。
一見食べるのを躊躇しそうなほど派手な色をしていますが、すべて天然素材で色付けされており、合成着色料は使用されておらず、安心して食べられます。



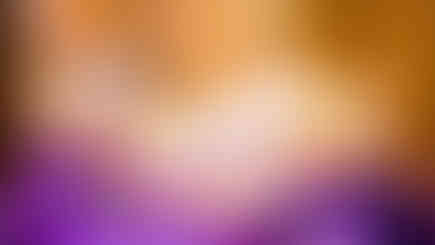







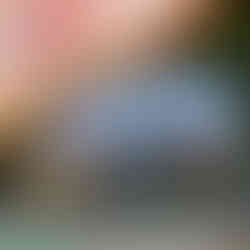



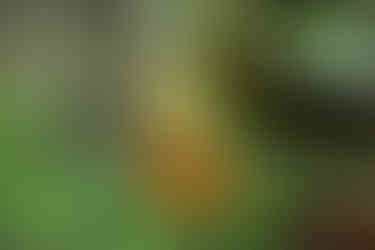

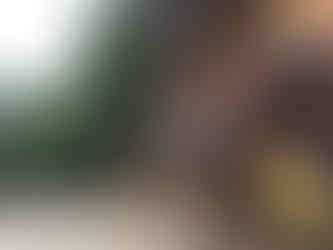

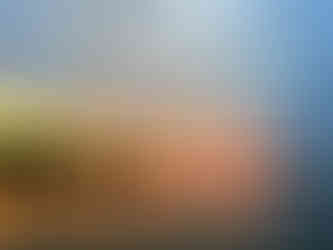














コメント